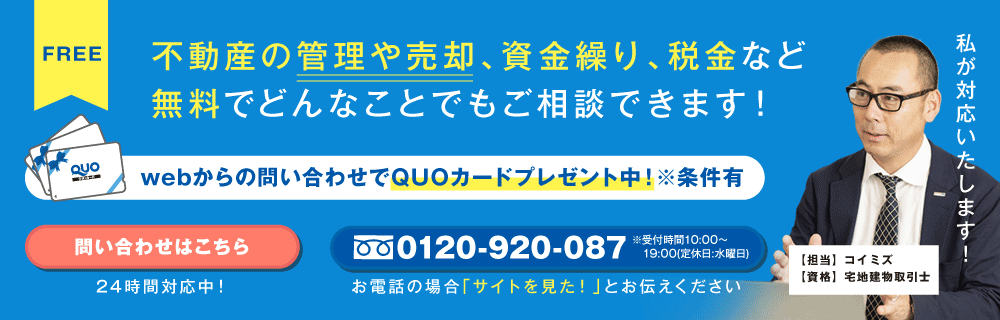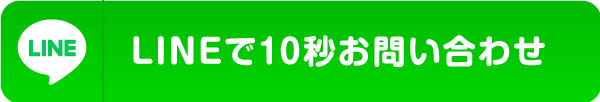こんにちは!KOBE(神戸)売却ナビの恋水です。地震大国・日本において、不動産オーナーが避けて通れないのが災害リスクのマネジメントです。特に神戸は、1995年の阪神・淡路大震災で大きな被害を受けたエリア。あの教訓を風化させないためにも、賃貸経営において今すぐ始められる備えについて改めて確認しましょう。この記事では、地震災害から物件と入居者を守るために、オーナーが準備できることを網羅的に解説します。
1. ハザードマップを活用してリスクを「見える化」する
災害対策の第一歩は、自分の所有物件の立地にどんなリスクがあるのかを把握することです。
ハザードマップとは?
ハザードマップとは、地震・洪水・土砂災害などの自然災害による危険区域、避難所、避難経路などを示した地図です。
国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、全国の自治体が提供するマップにアクセスでき、「重ねるハザードマップ」では、複数の災害リスクを重ねて確認できます。
- 国土交通省 ハザードマップポータルサイト
- 重ねるハザードマップ
入居者にも周知しよう
防災意識が高まっている一方で、入居者の約半数は「ハザードマップの存在を知らない」とする調査結果も。賃貸経営者として、入居者にも災害情報の共有をする姿勢が信頼感に直結します。
2. 築年数と耐震基準の確認:古い建物ほど要注意
「うちは新築時に建築基準を満たしているから大丈夫」と思っていませんか?実は、建築基準法は度重なる改正が行われており、築年数の古い物件では現在の耐震基準に適合していないケースも多く存在します。
耐震診断のすすめ
築10年、20年、30年以上経過した物件を所有している場合は、耐震診断の実施を検討しましょう。多くの自治体では診断費用の補助制度を設けています。
▶ 神戸市の補助金例(※2025年現在の情報に基づく)
- 木造住宅耐震診断補助:最大10万円
- 耐震改修補助:条件により最大120万円
![]()
事前にLINEアプリのダウンロードをされていない方はアプリのダウンロードが必要となります。
当サービスの利用が初めての方は「友だち追加」を行ってください。
3. 「特定建築物」の所有者が負う努力義務
1995年に施行された「耐震改修促進法」では、一定規模以上の建築物(賃貸住宅で3階以上かつ延床面積1000㎡以上)を「特定建築物」とし、耐震性能の確保に向けた努力義務が課せられています。義務とはいえ、耐震性の確保を怠ったことで地震被害が出た場合には、所有者の責任が問われるリスクもあります。保険だけでリスクを完全にカバーできるとは限らないため、早めの対策が重要です。
4. 防災情報の掲示と周知:入居者との信頼関係を築く
災害発生時には、的確な避難行動を取れるかどうかが生死を分けるポイントになります。
掲示すべき基本情報
- 最寄りの避難所までの道順・所要時間
- 避難所の住所と電話番号
- 災害伝言ダイヤル(171)やWeb171の使い方
- 無料Wi-Fi「00000JAPAN」の利用方法
物件の共用部や掲示板、入居時の資料などで事前に共有しておくと安心です。
5. 災害時の通信手段を確認しておく
被災地では電話がつながりにくくなるのが一般的です。そこで活用したいのが災害用伝言サービスや緊急Wi-Fiです。
代表的な災害用通信サービス
- 災害用伝言ダイヤル(171)
- 災害用伝言板(Web171)
- 各携帯キャリアの災害用伝言板
- 公衆Wi-Fi「00000JAPAN」
物件の案内板などで周知しておけば、入居者の安心感が高まります。
6. 管理会社との連携体制を確認しておく
実際に災害が起きた際、物件の状況や入居者の安否確認を担うのは管理会社です。緊急時に確実に連絡が取れるよう、災害対応マニュアルの整備や連絡ルートの確認を事前にしておくことが重要です。
7. 地震保険・家主保険の検討は次回へ
この記事では、地震災害に備えてオーナーができる準備を解説しました。6月の記事は、万が一の損害に備えるための「保険の活用」について詳しく解説します。
まとめ:地震災害への備えは、信頼される賃貸経営の第一歩
災害対策は、「まだ起きていないから大丈夫」ではなく、「起きる前に備える」ことが鉄則です。神戸のような大都市圏では特に、耐震性や災害対応力の高い物件が評価されやすくなっています。資産を守るだけでなく、入居者に安心して住み続けてもらうためにも、災害対策はオーナーの責任です。
お問い合わせはこちら
「うちの物件も耐震診断すべき?」「補助金について詳しく知りたい」など、お気軽にご相談ください。
事前にLINEアプリのダウンロードをされていない方はアプリのダウンロードが必要となります。
当サービスの利用が初めての方は「友だち追加」を行ってください。