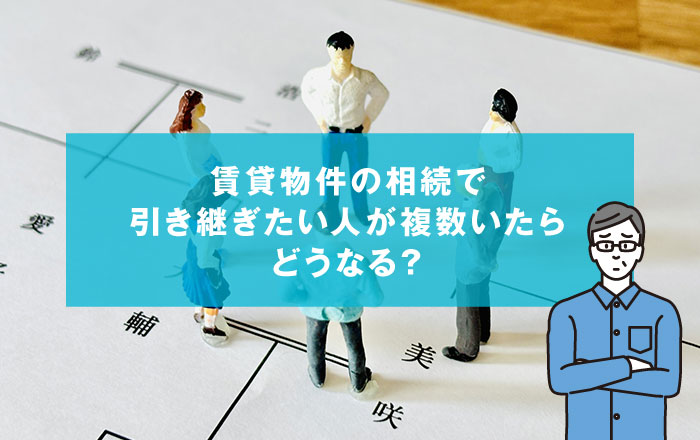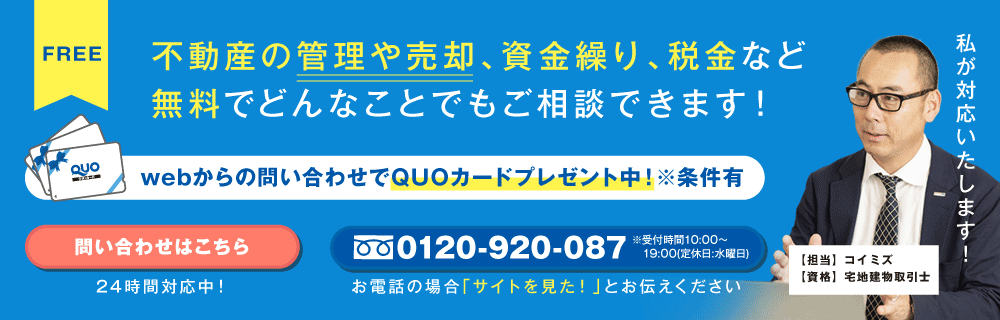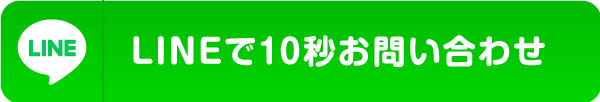こんにちは!KOBE(神戸)売却ナビの恋水です。賃貸経営をされているオーナー様にとって、「相続税対策」は避けては通れない課題です。その中でも最も効果が大きい節税策のひとつが【小規模宅地等の特例】です。この制度を正しく活用すれば、相続税評価額を最大80%も減額することが可能です。具体的には、相続税を数百万円〜数千万円単位で減らすことも夢ではありません。
小規模宅地等の特例とは?3つの分類に注目
この制度は、大きく次の3種類に分かれます。
| 種別 | 対象となる土地 | 減額率 | 限度面積 |
|---|---|---|---|
| ①特定居住用宅地 | 被相続人が住んでいた土地 | 最大80% | 330㎡まで |
| ②特定事業用宅地 | 店舗・工場などの事業用地 | 最大80% | 400㎡まで |
| ③貸付事業用宅地 | アパート・駐車場などの賃貸用地 | 最大50% | 200㎡まで |
この3つは併用可能であり、それぞれの上限面積まで適用することができます。
つまり、「自宅+アパート」「店舗+駐車場」などの組み合わせによって、最大限の節税が可能になるのです。
注意すべきポイント:貸付事業用宅地のハードル
アパートや駐車場などの「貸付事業用宅地」にもこの特例は適用されますが、面積上限が200㎡と小さめであり、他の2つと違ってより厳密な要件が課されます。
たとえば…
-
相続開始直前まで賃貸されていたか?
-
空室や改装中で「事業を停止していた」とみなされないか?
-
相続人が事業継続する意思を示しているか?
といった**“形式”だけでなく“実態”が重視**されます。
最近では、税務署がこの特例の適用要件を厳しくチェックしているため、「知らなかった」では済まされない時代になっているのです。
見相続対策の選択肢:「等価交換」という戦略
節税効果を高めるもう一つの手段が、**「等価交換(不動産交換特例)」**の活用です。これは、自分の土地と他人の土地を等価で交換し、かつ要件を満たした場合に譲渡所得税(売却益にかかる税金)を将来まで繰り延べるという制度です。
たとえば…
-
都市部の小規模な宅地に組み替えることで小規模宅地特例の効果を最大限に活かせる
-
築古アパートを現金化せずに別の物件に切り替えることで、事業継続と相続対策を両立できる
といった戦略が可能になります。
ただし、この方法には交換相手の確保・専門家のサポート・事前の計画立案が不可欠です。
不動産売却・買換えを視野に入れている方は、こうした制度を活かした提案ができる不動産会社や税理士に相談するのがおすすめです。
特例の適用が“無効”になるケースに注意!
「小規模宅地等の特例」は、要件を満たさないと一切適用されません。よくある失敗例を挙げておきます。
⚠️ よくあるNGケース
-
長期間の空室により「事業継続性」が疑われる
-
建物が老朽化し、実質的に賃貸していない
-
相続後すぐに売却・解体したため「継続の意思がなかった」とみなされる
-
土地が法人名義である(制度対象外)
相続税の申告後に税務調査で否認されることもあるため、制度を使う前提でしっかりと準備することが重要です。
まとめ:節税成功のカギは“事前の備え”にあり
「うちは大丈夫」と思っていても、実は要件を満たしていない…そんなケースも少なくありません。
小規模宅地等の特例は、適用されれば非常に強力ですが、制度の理解不足や準備不足で“使えなかった”という失敗も多いのです。
✔ 不動産の所有形態(個人か法人か)
✔ 実際の賃貸実績(空室率・稼働状況)
✔ 相続人の事業継続意志(形式だけでなく実態が重要)
これらをふまえ、相続のプロ(税理士や不動産コンサルタント)と連携して早めに対策を始めることが、納税負担の軽減と資産防衛につながります。
不動産売却・買い替えも有効な選択肢
なお、相続対策の一環として不動産の「売却」や「買い替え」を検討するのもひとつの方法です。
節税・収益性・相続しやすさ──複数の観点から今の資産構成を見直すことは、非常に有効な資産防衛手段です。
事前にLINEアプリのダウンロードをされていない方はアプリのダウンロードが必要となります。
当サービスの利用が初めての方は「友だち追加」を行ってください。