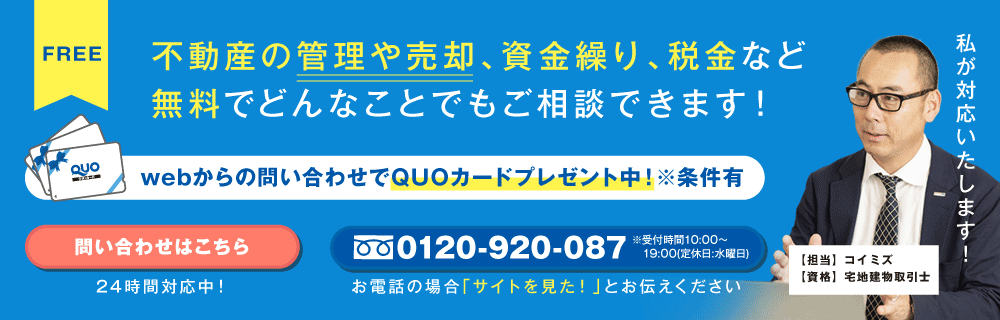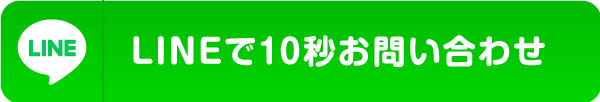こんにちは!KOBE(神戸)売却ナビの恋水です。賃貸物件を所有するオーナー様にとって、「誰に相続させるか」は非常に重要なテーマです。現金や株式とは異なり、賃貸用不動産は「使い方」が限られており、現物資産であることから分割が難しいという特性があります。さらに、安定した収益が見込めるからこそ、複数の相続人が「自分が引き継ぎたい」と希望するケースも少なくありません。
今回は、賃貸物件の相続時に「取得希望が競合した場合、どうなるのか」、また「相続トラブルを避けるにはどうしたらよいのか」について詳しく解説します。
相続時に賃貸不動産がどう扱われるのか
オーナー様が亡くなられた場合、所有していた賃貸物件は“遺産”となり、相続の対象になります。たとえば、戸建賃貸やアパートを所有していた場合、それらの「大家業」を誰かが引き継ぐ必要が出てきます。
このとき、相続人が複数いて「自分が大家業をやりたい」と主張した場合、どうなるのでしょうか?
まず、相続人同士で話し合って遺産分割協議がまとまれば問題ありません。しかし、希望が食い違ったり、条件で折り合えなかったりした場合は、家庭裁判所での「遺産分割調停」に発展することもあります。
調停に進んだ場合の2つの分割方法
家庭裁判所で調停が行われた場合、賃貸物件については主に次のいずれかの方法で解決が図られます。
- 代償分割: 一人の相続人が物件を取得し、他の相続人に対して代償金(お金)を支払う方法。
- 換価分割: 賃貸物件を売却し、その代金を相続人で分け合う方法。
もし複数人が「自分が取得したい」と主張した場合、それぞれが代償分割を希望している状態になります。このとき、最終的に「誰が取得するか」という判断基準に明確なルールはなく、個別事情を考慮して話し合いが行われます。
家庭裁判所で重視される判断材料
調停において「誰が物件を取得すべきか」を判断する際、家庭裁判所では以下のような要素を重視します:
- 相続人の年齢、職業、経済状況
- 被相続人との関係性
- 相続開始前の占有・利用状況(物件管理の有無)
- 財産管理能力や実績
- 物件を取得する必要性や活用計画
- 遺言に表れていない故人の意向
- 入札や譲歩の意志、取得希望の一貫性
特に重要視されやすいのが「生前の関与度」です。長年にわたって管理業務に関わっていた相続人と、まったく関わってこなかった相続人が同等に希望した場合、裁判所はやはり前者を優先する傾向があります。
相続トラブルを避けるための2つの対策
1. 遺言書を作成しておく
トラブルを未然に防ぐ最大の方法は、オーナー様が生前に「遺言書」を作成しておくことです。物件を誰に相続させるのかを明記し、その理由を一言添えておくことで、家族間の争いを最小限に抑えることができます。
「長男には長年管理を手伝ってもらったから、この物件は彼に渡す」といった具体的な内容があれば、他の相続人も納得しやすくなります。
2. 関心がある相続人は“実績”を作っておく
将来の取得を希望するのであれば、生前から物件管理や賃貸経営に関わっておくことが大切です。家賃管理、修繕対応、入居者とのやりとりなど、日々の業務に参加しておくことで、調停の際にも説得力を持った主張ができます。
まとめ
賃貸物件の相続は、感情的な問題と金銭的な価値が絡み合うため、トラブルが発生しやすい領域です。
相続時に「誰が引き継ぐか」で意見が割れた場合、調停に発展するリスクもあるため、できる限り早い段階からオーナー様とご家族がコミュニケーションを取り合い、準備を進めておくことが重要です。
トラブルのないスムーズな相続を実現するために、専門家のアドバイスも活用しながら、家族全体で前向きな相続準備を行いましょう。
事前にLINEアプリのダウンロードをされていない方はアプリのダウンロードが必要となります。
当サービスの利用が初めての方は「友だち追加」を行ってください。